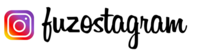02/05(水)【保健委員会】第5回学校保健委員会「救急法講習会(2年)」①
2月5日(木)4・5時間目 保健体育の授業内で 第5回学校保健委員会「救急法講習会」を開催しました。対象学年は2年生です。講師は 附属中学校 養護教諭(応急手当普及員)、指導補助として川口市消防局本部の職員6名 にお越しいただきました。生徒・教職員・消防局本部の職員 と人の命の大切さについて改めて考える時間とし、一次救命処置の知識やスキルを身に付ける機会(消防署が発行する「救命入門コース受講証」を取得する機会)としました。2年生の生徒保健委員と附属中救命リーダー(15名)が事前に準備を行い、生徒が指導補助要員として大活躍する学校保健委員会となりました。
〇附属中救命リーダーとは?
1学期終業式で行った 第2回学校保健委員会「中高合同救急法講習会」に参加した保健委員と各部活動代表生徒のことです。すでに一次救命処置を学び、スキルを取得済みの生徒です。※今回の会ではオレンジ色のビブスを着て参加しました。
詳細はこちら
07/18(木)【保健委員会】第2回学校保健委員会「中高合同救急法講習会」
今回の第5回学校保健委員会も保健委員生徒による運営で実施しました。
~開会の言葉~ 保健委員より
自分の目の前で人が倒れた時、倒れている人を見かけた時、どんな対応が適切なのかについて実践します。すでに保健体育の保健の授業で知識として得た内容を実際に行動に移せるようにしましょう。命の重み・大切さを実感してもらう機会でもあります。自分ごととして捉え、しっかりと取り組めるようにしましょう。
~開催目的の確認~ 救命リーダー代表者より
目的は「救命入門コース受講証」の取得と、附属中生全員が一次救命処置の知識・技術を習得することです。1期生の先輩の声から始まったこの取り組みは、今回で3回目となります。人が目の前で倒れた時、助けられるようになること、また命を助けるためにはたくさんの人の力が必要なことを体験したり、命の重みについて実感したりする会にしましょう。
~実技講習前講話(一部抜粋)~ 附属中養護教諭
中学生が一次救命処置に携わり活躍した事例を紹介しました。
さいたま市立中学校に通う中学生が、学校近くの商業施設を訪れていた際、女性が倒れるところを目にします。女性に駆け寄り意識がないことを知った生徒は、すぐさま119番通報しました。そして、次に行動したのがAEDを持ってくることでした。250m離れた中学校の校門まで走り、AEDを抱えて現場に戻りました。生徒たちや商業施設の関係者などの協力で、女性はその後到着した救急車に搬送され、一命をとりとめました。
勇気をもって傷病者に声をかける、意識がないと判断して119番通報をする、AEDの場所を予め把握し、走って取りに行く・・・これらの行動は一次救命処置の訓練を受けた経験と勇気があってできた行動です。
埼玉県の救急車到着時間の平均時間は7~8分と言われています。呼吸が停止してから1分でも1秒でも無駄にせず、すぐさま救助することが大切だということを理解したうえで実技講習がスタートしました。
この学校保健委員会の続きは
02/05(水)【保健委員会】第5回学校保健委員会「救急法講習会(2年)」2
をご覧ください。