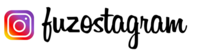07/18(金)【保健委員会】第2回学校保健委員会「中高合同救急法講習会(2年保健委員+部活動代表者)」
本校の特色の1つは、高校生と一緒の敷地内で生活していることがあげられます。中高生が一緒に保健に関する取り組みを通して、交流できる機会を作れないものか・・・という思いから、全日制養護教諭と附属中養護教諭が連携し、中高合同学校保健委員会「救急法講習会」を実施しています。毎年1学期の終業式の日に救命救急法と熱中症対策について中高生が一緒に学び、スキルを身に付ける機会を設けています。参加者は 全日制生徒(各運動部から1名、救命講習班の保健委員12名)と 附属中生徒(各部活動から1名、2学年保健委員6名)です。
今年度は、全日制養護教諭と附属中養護教諭が講師となり、シミュレーション訓練を取り入れた講習会を計画し、本番さながらの実践的な講習会を行うことが出来ました。
今年度は嬉しいことに、一貫生(附属中を卒業した高校1年生)も参加しており、元附属中保健委員の先輩が司会者となり、講習会の運営に協力してもらうことが出来ました。
〇内容〇
①救急法実技講習 60分 指導者:附属中養護教諭
②熱中症の予防と対応 30分 指導者:全日制養護教諭
〔①救急法実技講習〕
「2023年12月、さいたま市の中学校に通う中学生が、学校近くの商業施設を訪れていた際、駐輪場で子どもを連れた女性が倒れるところを目にしました。その中学生はすぐさま救助の行動をとりました。さて、みなさんならどのような行動をとることができますか?」という問いかけから講習会をスタートしました。
「とりあえず声をかけてみる」
「119番通報する」
「AEDを持ってきてくださいと言う」
「安全な場所に移動させる」 等、今自分にできることを答えてくれました。
さいたま市の中学生は女性に駆け寄り意識がないことを知り、すぐさま消防に通報しました。そして、次に行動したのがAEDを持ってくることでした。自分の学校の校門にAEDが設置されていると知っていた生徒たちは250m離れた中学校の校門まで走り、AEDを抱えて駐輪場に戻りました。そして、居合わせた大人がAEDを装着しました。
「プライベートでこのような場面に遭遇した時、部活動中に仲間の様子がいつもと違う時等、今回この講習会に参加するあなたたちも勇気ある行動をとれるようになって欲しい」と伝え、実技講習をスタートさせました。
1人1体人形を目の前に、一次救命処置の流れを声に出して、身体をつかって覚えていきました。
「人が倒れています!」
「周囲の安全よし」
「もしもし大丈夫ですか?」×3
「だれか助けてください!人が倒れています」
「あなた、119番通報をしてください」「あなた、AEDを持ってきてください」
「呼吸の確認 1・2・3・4・5・6 普段通りの呼吸なし」
「胸骨圧迫開始」 ※胸骨圧迫30回
AED使用について、ポイントを学んでから実際に音声にあわせてパットを貼る練習をしました。
・パッドの種類について:未就学児用パッド、小学生~大人用パッドがある。
・電気ショックについて:ボタンを押すタイプのAED、オートショックAEDがある。
・貼る際の注意点:プライバシーを可能な限り守りながら対応、AEDの音が聞き取れるように周りを静かにさせる。
AEDを貼っている最中も胸骨圧迫を続けることが大切です。
ショックボタンを押した後にすぐに胸骨圧迫を再開することが大切です。
〔②熱中症の予防と対応〕
熱中症の予防① 水分塩分補給
水分補給のタイミングは、
〇運動の前後
〇運動中は30分毎
〇授業の合間
熱中症の予防② 衣服の工夫
〇帽子や日傘で直射日光をカットする
〇通気性の良い服を着る
〇明るい色の服を着る
☆防具を付けるスポーツは、着用しているものを適宜緩めるなどして熱を逃がす
熱中症予防③ 生活習慣を整える
〇バランスの良い食事
(特に朝ごはんは絶対に抜かない)
※お味噌汁は、水分と塩分を同時に摂れるため朝食にオススメ!
〇十分な睡眠
〔参加した生徒の感想〕
~附属中生徒~
・AEDで心電図を解析できたり、自動で電気ショックを流すか判断してくれたりすることは知らなかったので、クラスの人にも伝えようと思います。胸骨圧迫をするときは思ったより強い力が必要で、確かに数人で救助する必要があるなと実感しました。部活中でなくても下校中も熱中症になる可能性はあるので、気温にあった服装や水分補給を心がけたいです。
・AEDや熱中症についての新しい知識を得ることができて良かったと思いました。また、自分は家の近くにあるAEDの位置を把握できていないので、それも把握するきっかけにもなりました。今日のこの講習で知ったことを生かし、熱中症や意識がなくなって危ない人がいたら、まわりを導けるようにしたいです。
・大事なのは胸骨圧迫やAEDの装着だけでなく、日ごろから対策や予防をすること、倒れている人がいた時は冷静な行動をとることが大事だと分かりました。
~全日制生徒~
・マネージャーとして、選手に対してできることがまた増えたと思うので、この会に参加出来て良かったです。
・一度中学校の時に救急法を学んだが不安だったので、今回学べてよかったです。心肺蘇生の際には、少しでも助かる確率を上げるために声をだし、周りと協力することが大事だと思いました。
・実際の救命現場の音声や具体例などを見て、一気に救急救命という事柄が身近になったように感じました。これから本格的に暑くなってきて体調管理をするだけではどうにもならない体調不良もたくさんあると思うので、自分が習ったことをみんなに伝え、部活の仲間全員が実行できるようにしたいです。
川口市立高校と附属中学校は毎年7月は救急法スキル強化月間です。実は中高の全教職員が今年も7月1日~7月3日の3日間、救急法講習会で訓練をしました。生徒も教職員も一緒の時期に救急法を学び、校内全体で意識を高めることができています。
教職員役、生徒役等の役割札を首からかけて、それぞれ与えられた役を演じました。
教職員も真剣に、緊張感を持ちながら傷病者発生の場面を想定して訓練しています。
中高の教職員もシミュレーション訓練を取り入れ、この講習会でも本番に近い形で実践的な講習会を行うことが出来ました。この講習会も毎年、全日制養護教諭と附属中養護教諭が連携して計画・実施しています。
今回の第2回学校保健委員会「中高合同救急法講習会」を通じて、もしものときに落ち着いて行動するための知識と技術を学ぶことができました。日ごろから自分の体調に目を向け、こまめな水分補給や適切な休憩を心がけることも、命を守る大切な行動のひとつです。これからの季節、熱中症にも十分注意しながら、自分自身や周囲の人の健康と安全を守る意識を高めていってほしいと思います。