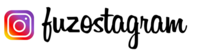07/04(金)【保健委員会】第1回学校保健委員会「食育教室」③~参加者の声(感想)~
こちらの記事は
「07/04(金)【保健委員会】第1回学校保健委員会「食育教室」②~専門家のご講演・体験活動~」
の続きです。
+α 情報 保健委員の発表の際に、新キャラクター「なすっち」の発表がありました。
生徒感想
【生徒の声①】「正しく食べて、健康的にダイエット」
西尾先生の講演で「食べるダイエット」という考え方を知り、衝撃を受けました。これまで、ダイエットは食べないことだと思っていましたが、必要な栄養素をきちんととることで、かえって健康的に痩せられるということを学びました。特にお菓子を食べながら炭水化物を制限するような偏った食生活は、体に良くないとわかり、自分の食習慣を見直す良い機会になりました。
【生徒の声②】「睡眠と成績の関係に驚き!」
講演の中で、睡眠時間がしっかり取れている方が成績が良くなる、という話がとても印象に残りました。私はこれまで、テスト前は睡眠を削って勉強することが正解だと思っていたので、驚きました。これからは、集中力を高めるためにも、まずは睡眠を大切にしたいと思います。お話が理科Ⅱの授業内容と重なっていたこともあり、興味を持って聞くことができました。
【生徒の声③】「家族の支えに感謝、自分も行動を」
体験活動でスープとおにぎりのメニューを考えてみたら、自分の考えた献立ではビタミンや鉄分がほとんど摂れないことに気づきました。毎日、栄養バランスを考えてご飯を作ってくれる母のすごさを実感し、感謝の気持ちが湧いてきました。これからは、食事の準備を手伝ったり、家族と一緒に健康的な献立を考えたりして、家庭での食生活にもっと関わっていきたいと思います。
【生徒の声④】「附属中だからこそ、意識したい健康管理」
附属中は給食がなく、歯みがきの時間もありません。そのため、一人ひとりが健康への意識を持つことが大切だと改めて感じました。保健委員の発表から、自分の生活を見直すきっかけにもなりました。歯みがきの習慣やカルシウム・ビタミンの不足、夜更かしなど…忙しい中でもできることから改善し、自分自身の健康を守っていきたいです。
【生徒の声⑤】「楽しく学べた!今すぐできることから実践」
講演ではキャラクターやスライドを使った説明が分かりやすく、楽しみながら多くの学びを得ることができました。保健委員の発表や体験活動も、現状を知るだけでなく、自分にできることを考えるよいきっかけになりました。中学生の今こそが成長に必要な時期。日々の食事や生活習慣を大切にし、今日学んだことを少しずつ実践に移していきたいです。
保護者の感想
【保護者の声①】「親子で学ぶ時間が家庭の会話と行動を変えるきっかけに」
子どもが興味を持って真剣に講演を聞いている姿に驚き、私自身もそれに応えたいと思いました。栄養について、親の私も新たな学びが多く、大変勉強になりました。親子で同じ時間を共有できたことが、家庭の会話や意識の変化につながっています。
子どもが「ジュースより牛乳」「おやつに小魚アーモンド」と行動に変化が見られ、専門家の話は子どもの心にも響いていると実感しました。
また、保健委員の皆さんの堂々とした発表にも感動しました。入学して間もない生徒たちが、自主的に行動している姿に頼もしさを感じました。
【保護者の声②】「『食』は成長の土台 家庭でもできることを少しずつ」
中学生のこの時期が将来の健康にとっていかに大切かを、改めて深く考える機会となりました。炭水化物が多めになりがちな家庭の食事を見直すきっかけにもなり、スープとおにぎりの取り組みを家でも始めようと思います。
とはいえ、毎日のお弁当づくりには限界があり、学食など学校のサポートもあると嬉しいです。手軽にできるメニューの具体例なども参考になり、「完璧を目指さず、できることから」という考えに救われました。
娘と一緒にスープの具材を考えながら、栄養バランスを意識する良い習慣が始まりそうです。
【保護者の声③】「専門的な内容もわかりやすく、心に残る講演でした」
西尾先生の講演は、専門的な内容を図解や具体例でとても分かりやすく伝えてくださり、保護者としても知識を深めることができました。脂質が脳に関わること、DHA・EPAや抗酸化作用の働きなど、理論と実生活がつながる内容が多く、学びの多い時間でした。
子どもたちが不足しがちな栄養素とその影響についても知り、質の良い食事を心がけようと再認識しました。
また、保健委員の発表がしっかりしていて、日頃の活動の様子がよく伝わりました。体験活動の時間も非常に有意義で、他の保護者の感想を聞けたことも参考になりました。
【保護者の声④】「お弁当生活の悩みと向き合うきっかけに」
給食がないことで、家庭の負担が大きく、栄養バランスが取れているか不安が常にありました。今回の講演で、栄養素の組み合わせや簡単な補食の工夫を学ぶことができ、お弁当にも取り入れてみようという前向きな気持ちになれました。
「サバ缶をストックする」「スープに工夫をする」など、すぐに実践できそうな工夫も紹介していただき、実用的でした。
保護者としては、時々でもよいので学食の活用や調理実習など、学校と家庭で協力できる仕組みがあるとより安心です。保護者会での声も大変参考になりました。
【保護者の声⑤】「日々の食事の意味を見直すきっかけに」
これまで漠然と「栄養バランスが大切」と思っていたものの、講演を通じてその背景や理由が明確になり、子どもにも伝えやすくなりました。
「睡眠時間を削って勉強するより、きちんと寝た方が成果が出る」といった言葉も説得力があり、親の声かけにも自信を持てるようになりました。
食育授業→家庭科の調理実習→講演→スプおにプロジェクトという流れも非常に自然で、学びが連続している点に学校の工夫を感じます。
「お弁当はただ作るもの」ではなく、「子どもの健康を支えるもの」と再認識できた、とても意義のある時間でした。
大学院生・教職員の感想
【大学院生の声】「学びを即生かしている附属中生は素晴らしい」
・今回体験活動をさせていただいて、とても楽しかったです。一人一人が調理実習や講演の内容を生かして、体験活動に取り組んでいる姿がとても印象的でした。ひとりひとりが自分事として考えており、プロジェクト期間の実践がとても待ち遠しいと思っていました。実際、プロジェクト期間に巡回し、お昼の状況を見させてもらいましたが、具だくさんのスープを持ってきている生徒が多く、西尾先生の講義や調理実習での学びを生かしている姿が見られてとても嬉しかったです。健康な食生活は、学校生活の土台となるものです。これからも学びを生かして、元気に学校生活を過ごしてください。
【教職員の声】「我が子への食を考えるきっかけに」
・西尾先生の講演は分かりやすく、楽しく、あっという間でした。娘がぽっちゃりしているので、炭水化物はご飯で摂るようすすめました。今日、生徒が「今日のお弁当自分で作ってきた!」と声をかけてくれました。素晴らしい取り組みです。
指導講評 新井 朋子教頭
ご多用の中、保護者の皆様にご来場いただき、誠にありがとうございました。参加希望の問い合わせが多く寄せられ、皆様の関心の高さを大変うれしく感じております。
埼玉大学の西尾尚美先生には、今年度も引き続きご指導をいただき、感謝申し上げます。本校の健康教育における大きな支えとなっており、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
大学院生の中田さんには体験活動の企画を、保健委員の生徒の皆さんには準備や進行、発表を通して、素晴らしい会の運営をしていただきました。生徒が主体となって健康への関心を高めていることに、本校の特色と力強さを感じました。
私は本校へ着任し、給食がないことに少し不安を覚えましたが、西尾先生のご助言や保健委員の取組を知り、安心できました。それでも今後も、生徒がしっかりと栄養を摂り、食や睡眠を生活の優先順位に置くことの大切さを伝え続けていきたいと考えています。
近年、社会全体において「ルッキズム(外見重視)」の傾向が強まり、思春期にある生徒の皆さんも、「ご飯をたくさん食べること」に抵抗を感じる場面があるかもしれません。しかし、成長期の今こそ、正しい知識に基づいて、しっかり食べることが大切です。
本日の講演では「睡眠」についても触れられました。食と睡眠は、学校生活を健やかに送るための基盤です。これらを生活の優先順位として意識し、自分自身の健康のために決断し、実践していく力を、附属中の皆さんにはぜひ身につけてほしいと思います。
また、しっかり食べるためには、健康な歯が欠かせません。海外ではむし歯になる前に予防的に歯科を受診する習慣がありますが、日本では症状が出てから通う傾向が強いといわれています。私自身も近年、口の健康への意識を改め、忙しくても定期的に歯科を受診し、毎日3回の歯みがきとフロスを欠かさないようにしています。
食や睡眠を大切にすることは、ご家庭でもすでに意識して取り組んでいただいていることと思いますが、本日ご参加いただいた保護者の皆様には、今回の内容をぜひご家庭に持ち帰っていただき、生活の中で一層実践を深めていただければ幸いです。
大切な生徒たちが、これからも元気に過ごせるよう、大人も子どもも一緒に、食・睡眠・歯みがきへの意識を高めていきましょう。本日はありがとうございました。
おわりに
今回の学校保健委員会では、生徒自身が「自分の食」や「歯みがきや睡眠等の生活習慣」について深く考え、発信する力を高めるとともに、専門的な知識を講演で学ぶことで、より具体的な行動につなげるヒントを得ることができました。
食生活は毎日の積み重ねによって形づくられます。完璧を求める必要はありませんが、小さな意識の変化が健康な未来への一歩になります。今後も、学校・家庭・地域が連携して、生徒たちの健康を育んでまいります。今後も本校の学校保健活動のご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。